自分に向いてる仕事が分からない時に適職がわかるMBTI性格診断の活用法!


どうも、こんにちは!
ご訪問いただき、ありがとうございます!もぴです。
転職したいけど、自分に合う仕事がなんなのかわからない。仕事でやりたいこともよくわからないし、転職に踏み出せない。こんな悩みはありませんか?
私も以前は、何が向いているのか?何にやりがいを感じて、どんな仕事なら強みを発揮して夢中で楽しめるのか…が、全くわかりませんでした。
でも、MBTI診断や、本音を明確にするジャーナリングノートに出会い、今ではキャリアだけでなく、恋愛・人間関係・ライフスタイル全般が満足100%の毎日に整えることができました。
今回は、MBTI診断を活用した、自分に合う仕事の見つけ方、ストレスがかかるから避けた方がベターな環境について紹介しています!
- MBTI診断ってなに?
- MBTI診断のタイプ別・仕事の選び方
- MBTI診断のタイプ別・ストレスのかかる環境

ぜひ最後までお楽しみください♪
MBTI診断で知る性格タイプ
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、心理学者ユングの理論をもとに作られた性格診断ツールです。人の性格を4つの軸で分類していて、その特徴から16の性格タイプに分かれています。

- 内向型(I)or 外向型(E):エネルギーをどのような形で補充するか
- 感覚型(S)or 直感型(N):情報をどう受け取るか
- 思考型(T)or 感情型(F):意思決定をどう行うか
- 判断型(J)or 知覚型(P):生活スタイルや計画性
の傾向がわかります
例えば、「INTJ」なら内向型・直感型・思考型・判断型を持つ人、という意味になります。
なぜ自己理解にMBTI診断が役立つのか?

MBTI診断が自己理解に役立つのは、自分の特性を客観的に把握できるからです。
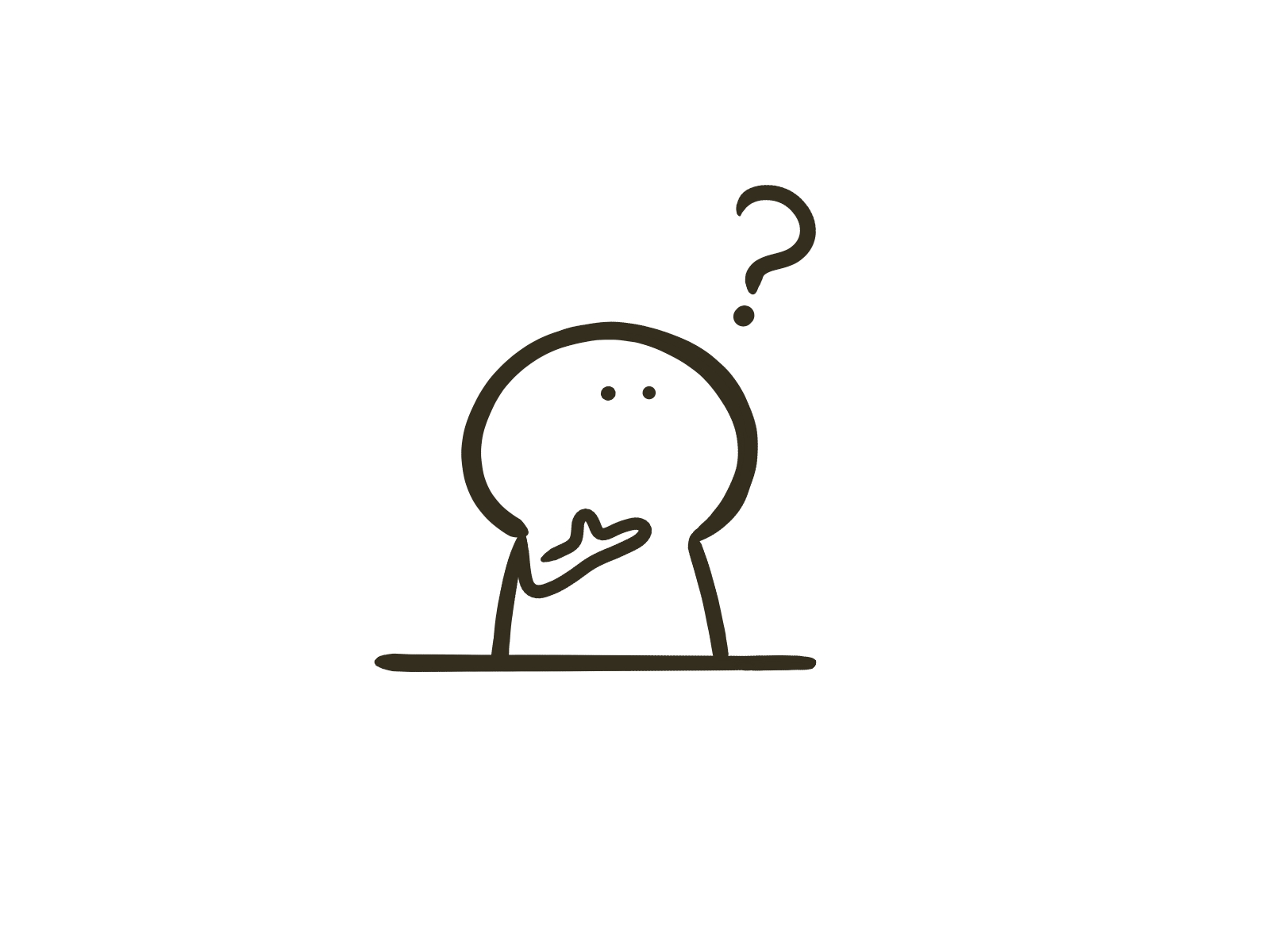
自分の性格に合った仕事って
なんなんだろう?
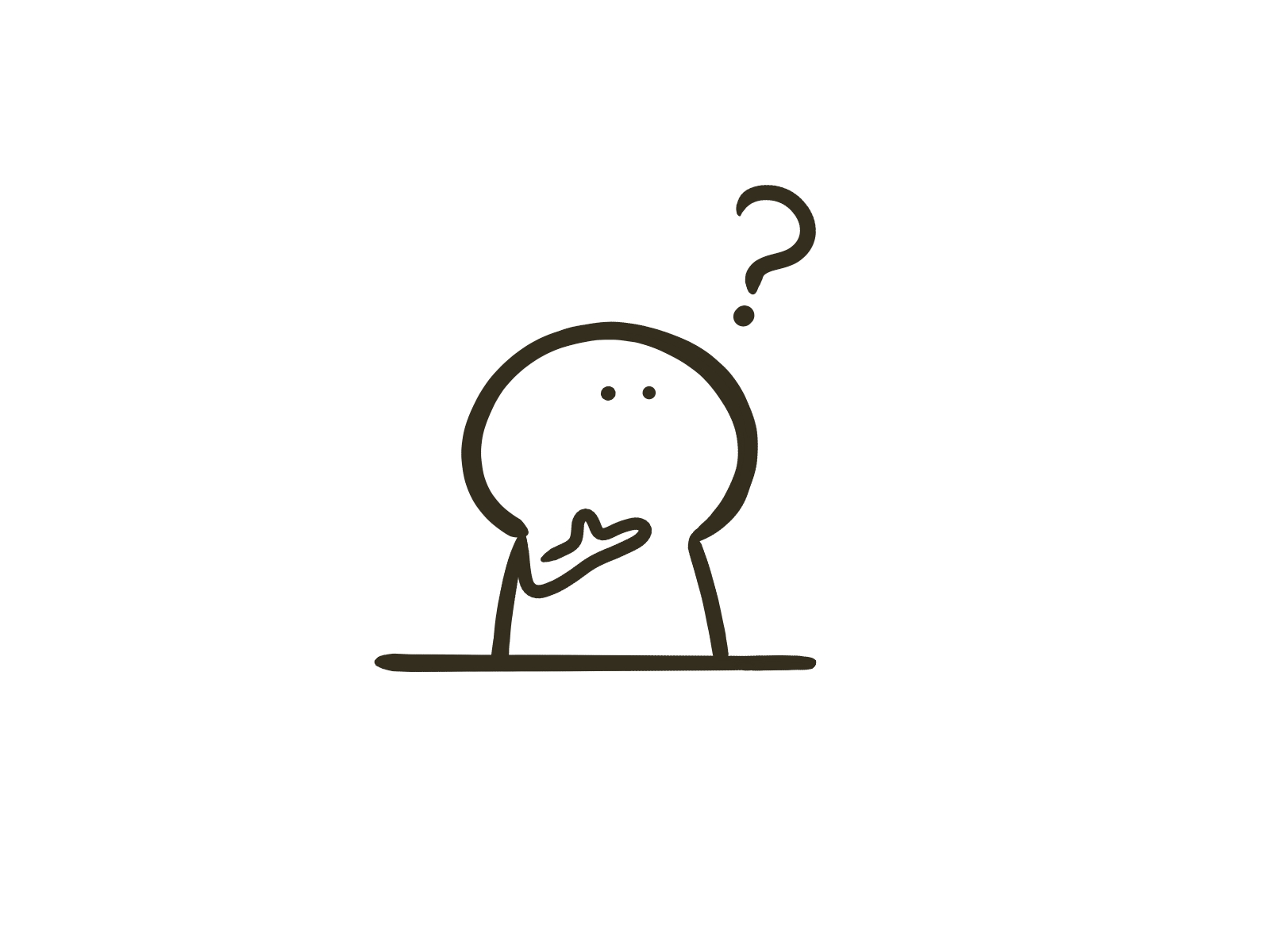
なんで自分はこれが出来ないんだろう?
みたいな疑問を解決できるヒントとなります。
そして、MBTI診断のように自分の性格がわかると、他人との違いも明確になります。
周りにいる人の行動の理由・言動・価値観の違いを理解できるようになり、自分を理解できるだけでなく、人間関係も良好になります。

社員の人事や、生産性をあげるチームビルディングに活用してる企業も多いですよね!
MBTI診断を仕事選びに活かす方法

仕事で、自分の得意を発揮したり、満足感を得ながらキャリアアップしていくためには、自分の性格に合った環境や役割を選ぶことが、めちゃめちゃ重要だと思うんですよね。
合わないことを頑張るのってストレスかかります。
昔から「努力は必要」とか「石の上にも3年」とか言われてますけど、魚が陸で3年頑張ったところで走れるようになりますか?って話です。
犬が本気で頑張ったって空は飛べないわけです。
でも人間は見た目が同じだから、「同じことができる」と思われちゃうし、自分でも「人が出来て、自分が出来ないのは努力や才能が足りないからだ」って思っちゃうんですよ。
どうせなら適切な場所で、才能を伸ばすための努力がしたいですよね。
MBTI診断でわかること
- 自分の強み
得意分野や能力を客観的に把握できます。例えば、論理的なTタイプは分析力が求められる仕事に向いている、臨機応変に動くのはPタイプが得意、といった感じです。 - ストレスを感じにくい環境
向いていない環境を避けることで、働きやすい職場を見つけることができます。 - 自分にピッタリ合ったキャリア
自分の得意なことや強みを活かせるキャリアの可能性を見つけやすくなります。
やりたいことをやろう!っていう風潮がありますけど、今までやりたいことを見つけてこなかった日本人にとったら、いきなり見つけにくいと思うんですよね。
自分に合わない場所・やりたくないこと・苦手なことを明確にして、まずはそれをなるべく排除していくことで、だいぶストレスは緩和されます
満足するキャリアには「自己理解」が欠かせない
キャリアにしても、人間関係にしても、恋愛・結婚にしても、満足100%の人生を選んでいくためには、自己理解って欠かせないと思うんです。
ただ単に「安定しているから」「給与が高いから」といった外側にある要因だけで選んでしまうと、自分の良さを封じ込めて働かないといけなくなり、ストレスや不満だらけの日々になってしまうんですね。

ちなみに、私自身はアイデア溢れる好奇心旺盛なチャレンジャー・ENFP(広報運動家)です。
それなのに「安定している」という理由でルールと規制がガチガチの公務員やってましたから…
幸い教育職だったんで、臨機応変さが求められるし、変化のある毎日ではあったんですけど、やっぱり自分の色を思い切り出せないストレスはありましたね。
MBTI診断で自分の強みや価値観を明確にするメリット

自分自身をよく理解していると、次のようなメリットが得られます。
- 自分の強みを最大限に発揮できる
人にはそれぞれ得意なことや強みがありますが、それを知らないまま仕事を選んでしまうと、力を発揮しにくい環境に身を置くことになる可能性があります。
MBTI診断を活用することで、自分の得意を自覚して、仕事に使えるスキルとして活かすことができますね。 - モチベーションを維持しやすい
自己理解が深まると、自分が「何にやりがいを感じるのか」「何を達成したいのか」など、モヤモヤしていた部分がハッキリと明確になります。
やりがいを感じられる仕事を選ぶことで、夢中でお仕事ができたり、高いモチベーションを保つことができます。 - ストレスを減らせる
自分の性格や価値観に合わない環境では、仕事のパフォーマンスが下がり、ストレスも増大します。
自己理解を通じて、自分が「心地よい」と感じられる働き方や環境を選べば、精神的な負担を軽減できます。

私はチームで働くより、一人でじっくり進める仕事が得意!

社会や人のために貢献できる仕事がいいなぁ…

あんまり人とかかわらずに、自分のペースで働ける環境が良いな!
あまり意識していなかったことを言語化することで、「どのような職場や職業が自分に向いているのか」を判断する基準ができ、後悔の少ない選択ができるようになります。
自己理解を深める具体的なステップ
- MBTI診断を受ける
オンラインで、10分程度で診断できます。自分のタイプがわかったら、そのタイプについての理解することで、自己理解がどんどん深まります。当サイトでも自己理解については記事を更新していくので、ぜひチェックしてくださいね!
MBTI診断のサイトはこちらです - 過去の経験を振り返る
「どんな時に楽しかったか」「どんな状況で成果を出せたか」「何に大きなストレスを感じたか」「自分らしいと感じるのはどんな場面か?」「どうしてもやりたくないことは何?」などを振り返ると、自分に合った仕事の条件が見えてきます。 - 他人の意見を参考にする
自分では気付いていない強みや価値観を、家族や友人、同僚に聞くことで、自分の見えていない部分を知ることができます。
内向型(I)と外向型(E)職場環境に求めるものの違い

では、最初の軸である「内向型(I)」と「外向型(E)」が、エネルギーの補充方法や対人関係のスタイルについてみていきましょう!

ここでは、内向型と外向型それぞれの特徴や、職場において求める環境の違いについて解説します。
内向型(I)の特徴と職場環境の好みの傾向
特徴
- 一人で深く考える時間を好み、エネルギーを内側から補充します。
- 少人数での対話や、集中して取り組める仕事に向いています。
- 意思決定に時間をかける傾向がありますが、その分熟考された結論を出します。
職場環境の好み
- 静かで集中できる環境
内向型は周囲の刺激に敏感なため、オープンスペースよりも個室や仕切りのある空間を好む傾向があります。 - 少人数でのチーム作業
大人数でのミーティングや、頻繁な対人交流はエネルギーを消耗させるため、必要最低限のコミュニケーションが好ましいです。 - 自主性を重視する仕事
決まったルールやマニュアルに従うより、自分のペースで仕事を進められる環境で力を発揮します。
外向型(E)の特徴と職場環境の好みの傾向
特徴
- 他人と交流することでエネルギーを得るため、活発なコミュニケーションが得意です。
- 新しい経験や多様な刺激を求める傾向があり、変化に柔軟に対応できます。
- 意思決定がスピーディーで、行動力が高いのが特徴です。
職場環境の好み
- 活発で社交的な環境
人と接する機会が多く、意見交換やブレインストーミングを行うような職場が向いています。人と話すことで思考が整理されていく傾向にあります。 - チームでの共同作業
仲間と共に目標を達成することにやりがいを感じ、大規模なプロジェクトにも積極的に取り組みます。 - 変化が多く刺激的な環境
ルーティワークよりも、多様な業務や新しい挑戦がある職場を好む傾向があります。
内向型がストレスを感じる環境
- 会議やイベントが頻繁で落ち着けない職場
- 過度なコミュニケーションを求められる状況
- 仕事量や時間に追われてじっくり考えられない場面
外向型がストレスを感じる環境
- 人と関わる機会が極端に少なく、さらに単調な作業が続く仕事
- 自分の意見やクリエイティブを表現する場が与えられない窮屈な環境
- 変化が少なく、ルーチンワークばかりの職場

内向型と外向型の違いを理解することで、自分にとって心地よい職場環境を見つけやすくなります。
直感型(N)と感覚型(S)の仕事へのアプローチと価値観の違い

次に、「直感型(N)」と「感覚型(S)」は、情報をどう受け取るかに関わる特徴です。この違いは、仕事への取り組み方や価値観に大きな影響を与えます。
それぞれのタイプがどのようなアプローチで仕事に向き合い、どのような環境で力を発揮するのかを詳しく解説していきます。
直感型(N)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 全体像を重視する:細かいことよりも、物事の全体像や大きなアイデアに着目します。
- 未来志向:現状よりも未来に起こる可能性や新しいアイデアに興味を持ちます。
- 創造的で柔軟な発想:固定概念にとらわれず、新しい視点を生み出すのが得意です。
職場環境の好み
- 革新性を求められる環境
新しいアイデアや独自の視点が歓迎される職場で力を発揮します。 - 自由度が高い仕事
マニュアルに縛られるよりも、自分の方法で問題を解決できる自由度がある環境が理想です。 - 変化に対応できる環境
ルーチンワークよりも、挑戦や新しい経験が求められる職場を好みます。
感覚型(S)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 現実的な視点を持つ:具体的なデータや事実を重視し、実践的なアプローチを取ります。
- 細部にこだわる:物事を一つひとつ確実に進める慎重さがあります。
- 現在志向:目の前の課題を確実に解決しようとする行動力があります。
職場環境の好み
- 秩序と安定がある環境
明確なルールやプロセスが整っている職場で力を発揮します。 - 具体的な成果が求められる仕事
実際のデータや数字を扱い、成果を明確に実感できる環境が向いています。 - 計画的なスケジュールがある環境
確実に進捗を管理できる職場が理想的です。
直感型(N)と感覚型(S)のストレス要因
直感型がストレスを感じる環境
- 細かいルールや手順に縛られる環境
- 新しいアイデアが歓迎されない職場
- 長期的なビジョンを無視される場面
感覚型がストレスを感じる環境
- 抽象的で曖昧な指示が多い職場
- 具体的な成果が見えない状況
- 計画が頻繁に変更される場面
直感型と感覚型の違いを理解することで、自分に合った仕事の進め方や環境を明確にすることができます。
思考型(T)と感情型(F)意思決定スタイルの違いと仕事に与える影響

次に「思考型(T)」と「感情型(F)」についてみていきましょう!これは、何かを決断する時に、どんなことを重視するかを示します。
この違いは、職場での判断や人間関係、問題解決のアプローチに大きな影響を与えます。

それぞれの特徴を理解することで、自分の適性や働きやすい環境を見つけやすくなるだけでなく、同僚や上司、部下との円滑なコミュニケーションにも役立てることができます!
思考型(T)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 論理と客観性を重視する:感情に流されず、事実やデータに基づいて判断します。
- 効率を優先する:目標達成のために、合理的な手段を選択します。
- 競争心が強い:結果を出すことにやりがいを感じるため、挑戦的な目標を好みます。
職場環境の好み
- 論理的な議論ができる環境
感情論ではなく、データや分析に基づいた話し合いが行われる職場が向いています。 - 明確な目標設定がある環境
ゴールが明確で、その達成に向けた評価基準がしっかりしている環境で力を発揮します。 - 挑戦的な課題がある職場
知的な刺激を受けられる場面が多いほど、モチベーションが高まります。
感情型(F)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 共感と調和を重視する:人間関係を大切にし、他者の気持ちを考慮して判断を下します。
- 人を支えることに喜びを感じる:個人の成長やチームの幸福に価値を見出します。
- 感情的なつながりを大切にする:職場でも、思いやりや信頼関係を築くことに注力します。
職場環境の好み
- 協力的で温かい職場
チーム全体で助け合う雰囲気があると、よりパフォーマンスを発揮できます。 - 人間関係を重視する環境
単なる結果だけでなく、そこに至る過程や周囲との関係性が評価される職場を好みます。 - 柔軟性がある環境
人の感情に配慮した対応が求められる場面で力を発揮します。
思考型(T)と感情型(F)の職場でのギャップ
思考型がストレスを感じる環境
- 感情に流されがちな議論や意思決定
- 明確なルールや評価基準がない状況
- 結果よりもプロセスが重視される場面
感情型がストレスを感じる環境
- 人間関係や感情が軽視される職場
- 冷たい態度や競争が激しい環境
- 他者への配慮が欠けたリーダーシップ
思考型と感情型がお互いを理解するためのポイント
職場では、思考型と感情型が互いの違いを尊重し、協力することが重要です。
- 思考型から感情型へのアプローチ:データや結果だけでなく、人の気持ちやチーム全体の幸福にも配慮する姿勢を示す。
- 感情型から思考型へのアプローチ:意見を感情論ではなく、具体的な根拠やデータに基づいて伝える。
思考型と感情型の違いを理解することで、自分の特性に合った仕事だけでなく、チームメンバーとの円滑な関係を築くことができます。
判断型(J)と知覚型(P)の、働き方の好みと時間管理の特徴

次に、「判断型(J)」と「知覚型(P)」についてみていきましょう!
ここは、生活スタイルや時間の使い方、物事への取り組み方を表します。この違いは、職場でのスケジュール管理や業務へのアプローチに直結しています。
判断型(J)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 計画的で組織的:ゴールに向けて効率的に進むための計画を立て、それを実行するのが得意です。
- 締め切りを重視:タスクの優先順位を明確にし、早めに終わらせることで安心感を得ます。
- 秩序を好む:予測可能な状況を好み、突発的な変更にはストレスを感じることがあります。
職場環境の好み
- スケジュールが明確な環境
何をいつまでにやるべきかがはっきりしている職場で力を発揮します。 - 安定性がある仕事
急な変更や予定外のトラブルが少ない業務を好みます。 - 責任を持って進められる役割
プロジェクト管理やリーダーとしての役割を任されるとモチベーションが上がります。
知覚型(P)の特徴と仕事へのアプローチ
特徴
- 柔軟性が高い:その場の状況や流れに合わせて行動することが得意です。
- 即興的な対応力:スケジュールに縛られず、必要に応じて計画を変更できる適応力を持っています。
- 新しい体験を好む:単調なルーティンワークよりも、変化に富んだ業務を楽しみます。
職場環境の好み
- 自由度の高い仕事
決められたルールに縛られない環境で、創造力を発揮します。 - 変化の多いプロジェクト
同じ業務を繰り返すより、新しい課題や状況に挑むことを好みます。 - 自分のペースで働ける環境
スケジュールや方法を自分で決められる職場が理想的です。
判断型(J)と知覚型(P)の職場でのギャップ
判断型がストレスを感じる環境
- 計画性が欠けた職場や、スケジュールが曖昧な業務
- 突然の予定変更や予測不能な状況
- 他人の遅延や締め切りを守らない態度
知覚型がストレスを感じる環境
- 固定されたルールや、厳格なスケジュールに縛られる業務
- 変化や柔軟性がなく、単調な作業が続く職場
- 自由な発想を制限される環境

まずは自分の気質に合っていないものを生活からなるべく取り除いて、ストレスケアすることをお勧めします!
まとめ
いかがでしたか?
それぞれのタイプによって、意思決定の仕方や、強みなどに特徴がありますよね!
あなたの強みやどうしても譲れない価値観を大切に♡自分に合ったキャリアを築けるよう応援しております!!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!この記事が、MBTI診断を通じて自分に合った仕事や働き方を見つけるきっかけになれば幸いです。


